水漏れ防止用電源コントローラ
みなさんご存じのように、OF水槽での排水管が詰まったりして水の流れが悪くなったり、止まったりすると、汲み上がった水が行き場を無くしてタンクから自由放水をしてしまうわけで...。Little Wavesのタンクもサイドフローとなり、今まで無縁だった水溢れの防止を行う必要が出てきてしまいました(保険に入ってないから、水漏れするととんでもない費用がかかってしまうので)。
 とりあえず、応急的に作ったのが、右の回路のコントローラです。まー、これでも十分機能を果たすので、なんの問題もないのですが、そこはやっぱり適当に作ったというかなんというか、プライドが許しません(むしろ、これくらい単純なほうが安全性は高いのかもしれませんが、やっぱりね...)。
とりあえず、応急的に作ったのが、右の回路のコントローラです。まー、これでも十分機能を果たすので、なんの問題もないのですが、そこはやっぱり適当に作ったというかなんというか、プライドが許しません(むしろ、これくらい単純なほうが安全性は高いのかもしれませんが、やっぱりね...)。SSRも適当に転がってるし5V電源(AC/DC)も転がってるので、もう少しまとも?なものを作ってみることにしました。
LittleWavesのタンクはメインタンクとリフジウムタンクにサンプからクーラを通った水がポンプアップされています。リフジウムはメインタンクより若干高い位置にあって、リフジウムの水はメインタンクにサイフォンの原理で流れ落ちるようになっています。サンプへの排水はメインタンクからサイドフローによって行われています。
 もし、リフジウムからメインタンクへのフロー管が詰まったり、メインタンクのフロー管が詰まると、メインタンクやリフジウムにサンプからから、ポンプアップする水が無くなるまで供給される羽目になり、かくして床に巨大な潮だまりが出現することとなります。
もし、リフジウムからメインタンクへのフロー管が詰まったり、メインタンクのフロー管が詰まると、メインタンクやリフジウムにサンプからから、ポンプアップする水が無くなるまで供給される羽目になり、かくして床に巨大な潮だまりが出現することとなります。これを避けるには危険水位を超えた場合にポンプを停止させなければなりません。LWのタンク構成からすると、メインタンクとリフジウムにサンプから海水が供給されるので、メインタンクまたはリフジウムタンクの何れかが危険水位を超えた場合、給水ポンプを停止しないと駄目ということになります。つまり、リフジウムの水位センサーとメインタンクの水位センサーのANDでポンプを停止させなければなりません。
AND回路だけを搭載するんだとすると、ANDゲート一個だけですんでしまいます。AND素子(IC)一個にゲートが4個入っているので、これではちょっともったいなさすぎます。そこで、蒸発分の水足用のポンプ駆動もフロートスイッチを使うことにて一緒にコントロールする事にします。ポンプ停止用のセンサー口2チャンネルと蒸発水給水用のポンプ駆動用センサー口1チャンネルの計3チャンネルにします。コントロールされる電源は2つで良いのですが、せっかくセンサー口が3チャンネルあるのでポンプ停止ようの回路は独立した単独回路に出来るようにすることとして、コントロール電源も3つにする事にしましょう。ポンプ停止回路は反転出力も出来るようにして、ついでにLEDも点けてON/OFFで点灯/消灯するようにします。
というわけでまずは回路図です。もの凄く単純でいい加減な回路です。貧乏性なので、ロジック部は論理IC2ヶとアナログスイッチ1ヶでいけるように設計して、あとは運用で何とかするようにしてしまいました(本当はあと2ヶぐらいICを増やすともっとまともなのが出来るのですが、配線もめんどくさくなるので...)。
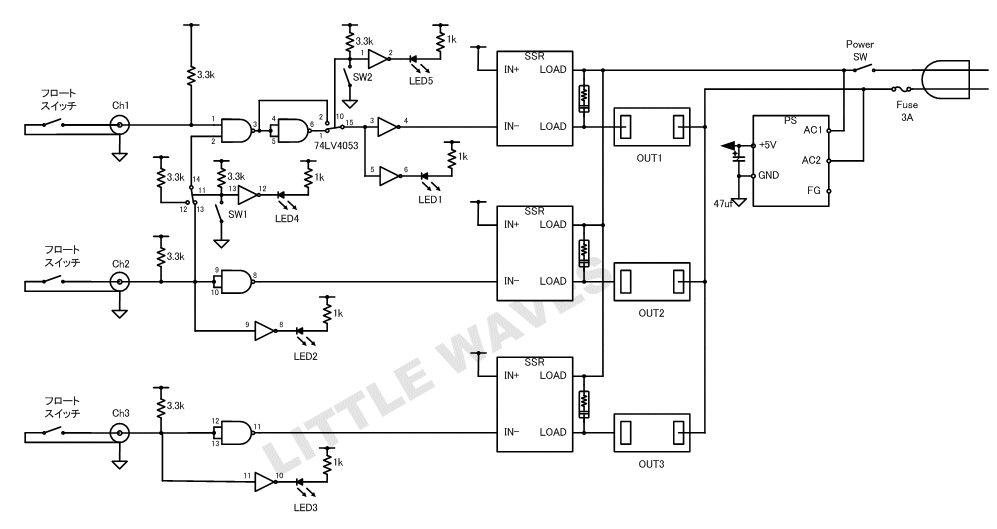
説明するまでも無いと思うのですが理屈的には、電源(OUT1〜3)のON/OFFを制御入力(CH1〜3)でコントロールします。OUT1が汲み上げポンプの電源用、OUT3が蒸発水給水ポンプ用、OUT2はおまけとなっています。
見てのとうり制御入力部はプルアップにしてあり、フロートスイッチがOFFの時(またま未接続の時)には電源がONになるようになっています。入力部の仕組みを逆にすると、フロートスイッチがOFFの時は電源をOFFにする事が出来ます。
OUT2とOUT3はCH2とCH3のON/OFFによる直接コントロールで、制御入力がOFF(またはNC)のときは、電源がONになります。制御入力がOFFの時に電源がOFFになるようにすには、
見てのとうり、フロートスイッチ接続口の部分はプルアップ状態にして、オープンでも、安定するようになっています(フロートスイッチがONすると入力段がLoになります)。
入力と出力の関係は下記の論理式のようになります。


 レイアウトは左のような感じでしてみました。
レイアウトは左のような感じでしてみました。フロント側には、ケーブル類が一切でないようにしてみました。深い意味は無いのですが、背面側に全てを集めてしまった方がコントローラを置く際にケーブル類をまとめやすいので、こんな感じになりました。電源のパワーライトが全面にあったほうがいいとか色々な好みがあるでしょうから、適当にアレンジしてください。
一応この図面は原寸で作成してあります。左の図面をDLしてビュワー等で印刷してもらえば、原寸になると思います。原寸にならなかったら済みません ^^;。
まー、こんなもんを作ろうと思う方は適当に腕に自信のある方々でしょうからあまりアドバイスする必要はないと思うのですが、レイアウト図を切り取って両面テープでシャーシに貼り付けて加工するのがよいかと思います。
穴開け加工すると、こんな感じになります。

 配線を行って、取り付けたのが左の写真です。
配線を行って、取り付けたのが左の写真です。一寸わかりにくいかもしれませんが、AC/CDがひっくり返しで基盤に取り付けてあります。SSRは秋月のキットを使ってしまったので、これを3つ取り付ける分の空間が必要だったのですが、色々と加工するのがめんどくさかったので。基盤をAC/DCとスペーサーで浮かせてその下にSSRを潜り込ませることにしました(ちょうど基盤のBNCの間に一寸だけ顔を出しているのが分かると思います)。
一応取り外しを考えてLEDへの接続はピンソケットを使って取り付けてあります。
お恥ずかしい限りではありますが、配線とレイアウトはかなりやっつけで適当な感じでやってます。皆様が作成されるときは、もう少しきちんとレイアウトをした方が良いかもしれません。もしも、詳しいレイアウトが知りたい(またはレイアウト図が必要)という方はご連絡くだされば提供します。ただし、かなり汚いレイアウトですよ!!
組み上がった段階で最終的な動作検査を行って完了です。
電源を入れる前に必ずショートのチェックや配線チェックはしましょう!
完成したコントローラです。背面側からと、正面側からの写真です(後は適当にレタリングをして終わりです)。

部品は結構ありもので作っているので、かなりいい加減ですが一応部品表です。
記号 名称 数量 IC2 74LS00 1 IC1 74LS04 1 SW3,SW4 74LV4053 1 C1 4.7μF 電解コンデンサ 1 R0,R1〜R5 1kΩ 1/4W カーボン抵抗 5 R6〜R11 3.3kΩ ネットワーク抵抗 1 SSR SSRキット(20A 秋月) 3 LED0,LED4,LED5 ブラケット入りLED 凸赤 3 LED1,LED2,LED3 ブラケット入りLED 凸緑 3 スパークキラー 3 Ch1,Ch2,Ch3 BNCコネクタ 3 3A ヒューズボックス 1 3A ヒューズ 1 ICソケット(14P) 2 ICソケット(16P) 1 PS AC/DC (5V 1A) 1 SW1,SW2 4CH DIP スイッチ 1 OUT1,OUT2,OUT3 AC コンセント(S2-726B) 3 Power SW 電源スイッチ 1 ACコード 1 ケース(130mm×110mm×60mm) 1 ユニバーサル基盤 1 スペーサ 15mm (SSR固定用) 6 スペーサ 25mm (基盤固定用) 2
 追加(改造部追記)
追加(改造部追記)
作成した後でふと気がついたんですが、初期設計ではCH3は足し水用の電源コントローラで、この回路は完全に独立回路となっています。このままでも良いといえば良いのですが、汲み上げポンプが停止しているにもかかわらず、給水用のポンプが動作するのは何だかよろしくないので、汲み上げポンプが停止した場合は給水ポンプも停止するように改造しました。部品点数は変えずに配線のみを変更したので、多少回路図が変ですが、OKでしょう。実際には、汲み上げ用のポンプが停止する時はサンプの海水をかなり汲み上げてしまっているので、サンプには相当量の給水が行われてしまう事になり、この状態で、排水が正常に戻ったりするとやっぱり部屋の中にはタイドプールができてしまうのですが...。完全にコントロールするには、センサーである一定以上に水位が下がったときも給水を行わないようにするか、比重計に連動してコントロールするしかないですね。
改良版の図面です。
見てもらえば分かると思いますが、OUT1がOFFになるとOUT3も強制的にOFFになる仕組みにしました。
